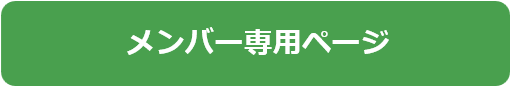ヴィンデルエルヴェン

ヴィンデルエルヴェン流域(スウェーデン)の事例
🌿 里山の風景
この地域には、7つのトナカイ放牧コミュニティの放牧地があります。それ以外にも、森林伐採、観光業、農業、大企業や小企業、エネルギー開発、鉱山や資源の探査、そして自然保護区など、さまざまな土地利用がされています。
また、この地域はハイキング、狩り、スキー、釣り、ベリー類やキノコ採りなどのレクリエーションにも利用されています。
トナカイ放牧は、遊牧的に移動しながら行う伝統的な家畜の飼育方法で、北極圏の文化の代表例の一つです。他の地域の遊牧にも似ています。山岳地域はトナカイ放牧が続けられてきたおかげで、比較的自然が守られています。一方、森林や沿岸の地域では、大規模な林業などによって開発が進んでいます。
トナカイ放牧はルールと規制の中で行われており、伝統を守りながら生活を続けています。
⚠️ 課題と脅威
スウェーデンでは、歴史的に「個人の土地所有権」が重視されてきました。そのため、昔からあった「共有地」は減っていきました。
しかし、スウェーデン北部の「ラップランド地方」では、先住民であるサーミの人々が、トナカイ放牧のために大きな土地を共有して使う権利を法律で認められました。一方で、サーミの人々が個人で持っていた土地はなくなっていきました。
その結果、トナカイの放牧地は、経済的にもとても大事な資源となり、地域の中で「共有のしくみ(コモン・プロパティ)」が作られました。
しかし、開拓が進む中で、民間の土地所有が増え、共有地と個人所有地が混ざりあった「並行する土地利用」が生まれました。これが現在、山のふもとの地域で続いており、伝統的なトナカイ放牧の生活(夏は山、冬は海辺へ移動する)を継続するうえで大きな問題となっています。
さらに、森林伐採や観光、エネルギー開発など、他の土地利用との競争も問題です。そして、気候変動によって放牧地の自然環境は大きく変化していくと予測されており、トナカイ放牧も大きな適応・対応を求められる可能性があります。